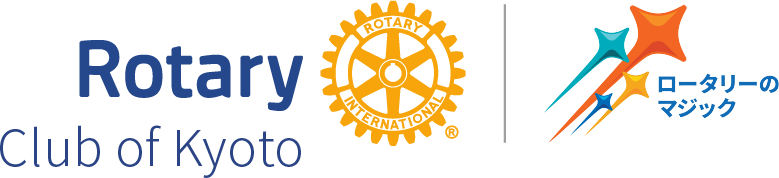|
2023.1.18
「不便益とは」
京都先端科学大学 工学部 教授
川上 浩司 氏
私が大学生の頃には「便利で豊かな社会を!」という言葉が世の中にあふれていた。私自身もそれを違和感なく受け入れていたし、工学部の学生として、「それが工学の使命ではないか」とさえ思っていた。便利=益、不便=害を前提に考えていたのだ。
ところが、不便を「手間がかかり、頭を使わねばならないコトやモノ」と定義してみると、「便利ならいい」という考えに疑問が浮かぶ。
便利にしてしまうと残念なものを想像してみよう。例えば「ねるねるねるね」というお菓子の改良型はどうか。このお菓子は粉末に水を加えて練り、飴状にして食べる。これを改良して「ねるねるねるね、練っときました」にすると、ユーザーの手間は省けるが、物足りなさが残る。
「プラモ、組み立てときました」という商品を作ったとしよう。プラモデルを自分で組み立てるユーザーの楽しみは奪われてしまう。
しんどい思いをして富士山に登る人のために、「富士山エスカレーター」があったらどうか。乗っているだけで頂上に着くのは楽しいだろうか。
このように考えていくと、不便で良かったこと、不便だからこそ得られる益がみえてくる。それを私たちは「不便益」と呼んでいる。
例えば、「クルマのドアの鍵はリモートでなく、差し込んで回すほうが、鍵をかけた実感がある」「原付が故障したので徒歩で通学したら、食堂を発見。その後お気に入りの店になった」「遠足のおやつは300円までと制限されると、時間をかけて選ぶ」といった事例があてはまる。つまり不便さは、可視性を高めて安心感を与える、気づきや出会いのチャンスを広げる、能動的な工夫を生む、モチベーションを向上させる、といった益を生むことがわかる。
不便益は、昔を懐かしむ単なるノスタルジーではない。物事のデザインに不便益を積極的に活用する取り組みがすでに始まっている。山口県のデイケア施設では、日常になにげないバリアをあえて作り、身体能力を衰えさせない「バリアアリー」を実践している。自分の足で漕ぐ車いす「COGY(コギー)」などもある。不便益を生むデザインが幅広い分野で提案されている。
これからも、社会の役に立つ「不便益を生むデザイン」について研究を深めたい。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|