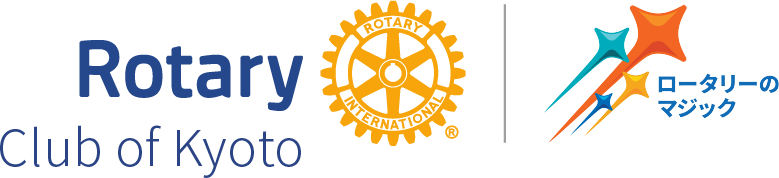|
2019.3.20
「京都の工芸―陶芸家・石黒宗麿の作陶風景から」
京都精華大学 伝統産業イノベーションセンター長
米原 有二 氏
縁あって、陶芸家・石黒宗麿の調査研究を昨年から始めた。彼は50年前に亡くなり、その工房跡は現在、京都精華大学が管理している。
石黒宗麿は、初の人間国宝に認定された陶芸家の一人だ。鉄釉陶器、鉄に由来する釉薬の使い方に優れ、しっとりとした暗い色の作風が評価されている。
彼は明治26年、富山県(現在の射水市)に生まれた。25歳の時、偶然目にした「曜変天目茶碗」に魅せられ、陶芸家を志したという。紆余曲折を経て、昭和2年に京都へ。窯やろくろ場の多かった東山山麓で陶芸を始めた。この頃に、陶芸研究家の小山富士夫氏と出会った。
昭和11年には八瀬に移り、住居兼工房の「八瀬陶窯(やせとうよう)」で作陶を続けた。京都の伝統的な陶芸界との交わりはあまりなかったが、北大路魯山人など個性の強い友人とは囲炉裏を囲んで酒を飲むこともあったという。
彼は誰にも師事しなかった。その石黒が大きな影響を受けたのは、中国の古代陶磁器だ。
実は、京都で出会い親友となった小山富士夫氏は後に、中国の宋代に名品が作られた定窯(ていよう)という有名な窯の場所を特定した。世界的な大発見をした小山は帰国すると、東京へ報告に行くより先に、八瀬の石黒を訪ねた。小山が定窯跡から持ち帰った陶片を見た石黒は、それをまぶたの裏に焼き付け、そのあと作品づくりの教科書にしたのではないか、と考えられる。
完璧主義者だった彼は、100点作っても残すのは5点ほどだったという。同時代の作家に比べて現存する作品は少ない。「八瀬陶窯」跡には、失敗作として割ったと思われる陶片がものすごくたくさん残っていた。
昨年6月には、残された登り窯の内部から「木葉天目茶碗」の完品が発見された。本物かどうかも含めて調査を重ね、今のところ、石黒の作品で間違いないだろうということで落ち着いている。茶碗の底に木葉を焼き付ける技法も、ルーツは宋代にある。晩年も宋の陶芸に憧れ、新しいチャレンジを続けていたと考えられる。
昨年、石黒の陶片を整理して大学内で展示した。割って葬ったものなど展示するな、とご本人は怒るかもしれないが、若い人たちが巨匠の失敗作から学ぶものは多い、と考えている。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|