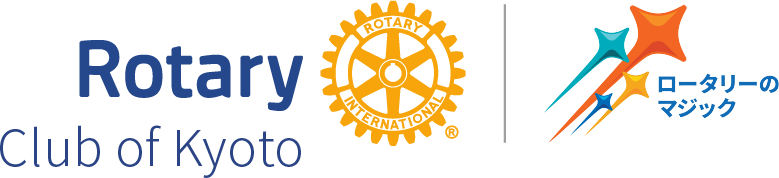|
2017.2.1
― 新会員スピーチ ―
「京の節分」
宗教法人 壬生寺 副住職
宗教法人 唐招提寺 執事
松浦 俊昭 君
大寒が過ぎ暦の上で春を迎える2月の立春には、京都の社寺は節分行事で賑わう。「おとしこし」とも呼び、京都では正月よりもこの時期の節分を重んじる人もいるくらいである。昔は各家庭で、鬼に扮した家長を子供達が豆をまいて追い払う豆撒きが行われ、食事では鰯を食べるなど節分独特の儀式が行われていた。豆は「魔を滅する」に通じる、或いは「マメに過ごす」などといい、節分になくてはならない食品である。しかし近年の節分には豆撒きもなく、流行の丸かぶりのお寿司を食べるだけ、という家庭も現れるようになった。核家族化が進んで家族の在り方が変わるに伴い、昔ながらの儀式がなくなりつつあることは非常に残念である。また、節分に社寺を参詣する意義を伝えることも次第に薄れてきている。
数ある社寺の中でも、京都の年中行事の一つに数えられる壬生寺の厄除け節分会(せつぶんえ)は、白河天皇の発願によって始められたといい伝えられ、930年もの永い伝統を持つものである。当寺は各社寺の中でも、京都の裏鬼門(南西)に位置し、京都の節分鬼門詣りの一端を往古より担っている。ご本尊は延命地蔵菩薩であり、お地蔵さまの誓願である庶民大衆の除災招福を祈願して、三日間にわたり古式により節分厄除け大法要を厳修している。期間中は、各地より参詣する老若男女で境内は大層にぎわう。壬生狂言を鑑賞する、或いは露店で楽しむなど。
壬生狂言「節分」は1日8回上演する。この狂言は「鬼(病気、災厄や貧困など様々な不幸)を招く甘い誘惑に負けずに、マメ(まじめに、こつこつ)に働くことによってこそ、福徳は得られるものである」と教えている。
壬生寺では「炮烙奉納」という独特の厄除けがある。近年、日本料理の器としても用いられる炮烙に、自身や家族の数え年と性別を墨で書き、奉納する。炮烙に自らの厄を移すことによって、厄除け開運を祈願する。奉納された炮烙は壬生狂言「炮烙割」で舞台の上から落として割るのである。
正月が暦の上でのスタートなら、節分はこのように「これから始まる新しい1年が、不幸や災いが無い1年になりますように」と願う庶民の心のスタートなのである。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|