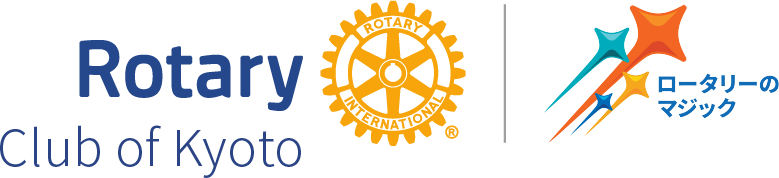|
2015.1.21
「実はあまり知られていないかるたの歴史」
(株)大石天狗堂 代表取締役社長
前田 直樹 氏
「かるた」という言葉は日本語ではありません。安土桃山時代にポルトガルから鉄砲などの南蛮文化が日本に伝来した時に一緒に伝わっています。当時は「南蛮かるた」と呼ばれており「かるた」という言葉もポルトガル語です。意味は「紙で作ったもの」で、英語でいうと「カード」と同意義です。
「南蛮かるた」は今で言うトランプに近いもので、これを元に国内で初めて作られたかるたが「天正かるた」と言われています。こちらは現物が2枚しか残っておらず、全体像はわかりません。その次に作られたものが「うんすんかるた」と言われています。現在でも製造されている物ではこの「うんすんかるた」が最古となります。
ゲームには賭博がつきものですが、かるた遊びも例外ではなく、一般大衆の娯楽と共に賭博にも使用されるようになりました。うんすんかるたやその他のかるたも爆発的に普及し、江戸幕府は1789年の寛政の改革でかるたを全面的に禁止します。それでも大衆はめげず、別のかるたを作っては幕府に禁止されるというイタチごっこになっていきます。その中で生まれたのが「花かるた」、今で言う「花札」です。この花札の一番の特徴は世界でも他にない数字の無いカードというところです。旧暦ですが、日本人なら見て直ぐに数字が連想できるよう四季の花々をデザインに使った傑作の意匠です。(数字を使ってないので賭博用の札では無い、という言い訳のためかもしれません)寛政12年(西暦1800年)に創業した弊社「大石天狗堂」も禁止令の中、表向きは米問屋を営み、裏でひっそりと花札を製作販売しておりました。明治時代にようやくかるたが解禁になりましたが、そのかわり骨牌税という税金を課せられ、これはトランプ類税と名を変え平成元年まで続きます。
近年、メディアの影響などで競技かるたの人口が増加し、また百人一首などは教科書に採用されるなど、一見して明るい話題が多いですが、玩具として家庭内でかるたで遊ぶという機会は減っていると思われます。かるたは老若男女問わず、またひとりでは遊ぶことが出来ないので、ぜひコミュニケーションツールとして使用されることを願います。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|