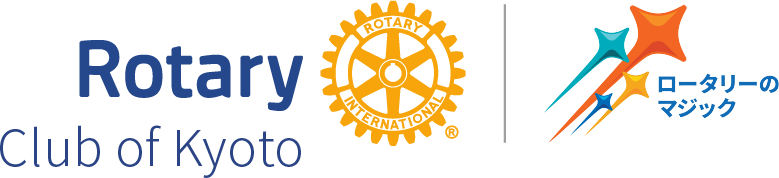|
2014.10.22
「京の御火焚と大根焚」
佛教大学 歴史学部 教授
八木 透 氏
京都の祭りや行事には、春から夏にかけては「水」の信仰にまつわるものが多い。晩夏から秋冬にかけては「火」の信仰が目立つ。今夜の「鞍馬の火祭」もその一つ。
京都は江戸時代に何度か大火があった。天明の大火(1788年)は、京都の町の4分の3を焼いた。人々は火を畏れ、火伏せの神・愛宕山に参詣して火伏せを祈った。
いまも賑やかな伝統行事に「御火焚(おひたき)」がある。こちらのルーツは「庭火」で、旧暦の霜月に、宮中で神を迎え神楽を奏したとき焚いた篝火のことだ。
『滑稽雑談(こっけいぞうだん)』という18世紀初頭の資料によると、朝廷からの官位を持つ神社で催される御火焚は、秋の実りを神に感謝する「新嘗祭(にいなめさい)」に相当する行事だったそうだ。だから、宮中の新嘗祭が御火焚のルーツとも考えられる。私が子供の頃、御火焚の日に供える「御火焚饅頭」「焼きみかん」のおさがりがいただけて、とても楽しみだった。
12月の「大根焚(だいこだき)」は御火焚の系譜に入る。
鳴滝・了徳寺では毎年、3000本の大根が振る舞われ(有料)、2日間で完売する盛況さだ。親鸞聖人が清滝に向かう途中、同寺に立ち寄ったとき、村人が旬の野菜である大根を炊いて、もてなしたのが由来だと伝えられている。
冬至の頃は、太陽のエネルギーが一年のうちで最も衰え、人間の生命力が枯渇する季節だ。そこへ尊い神様がやってきて、人々に幸をもたらすという「来訪神信仰」が日本には古くからある。その多くは親鸞聖人や弘法大師など高僧が来訪した伝承と重なって、行事として伝わっている。その神様への供物(施し物)が大根だが、火で焚いたものであるところが重要といえよう。なぜならば、「御火焚」の火、神を祀るための火に由来しているからだ。
京都では来訪神信仰と仏教の教えが融合して、施しによって功徳を積むという信仰に発展し、祭りや行事になったのだろう。それは京都庶民の信仰心の表象だといえよう。祭りや行事の本来の意味を考えながら、京都の祭りや行事をお楽しみいただきたいと思う。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|