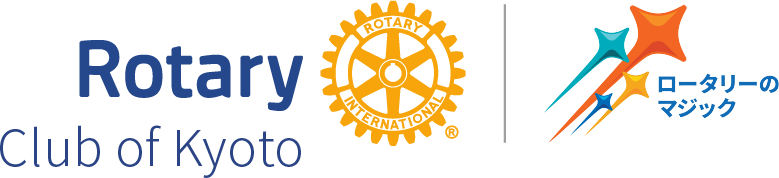|
2010.2.17
―新会員スピーチ―
「2010年の経済金融情勢」
日本銀行 京都支店 支店長
会員 金田一 弘雄 君
世界経済の現状をみると、米国における2つのショック(サブプライムローン・ショック、リーマン・ショック)の「目覚まし効果」によって、最早、米国経済が過剰借入・過剰消費体質のまま世界を牽引する構図は持続可能でないことが明らかとなった。これらのショックの煽りを受けた欧州が米国経済とともにバランスシート調整過程に入った一方、中国をはじめとするBRICsなどの新興国が世界経済の牽引役に入れ替わりつつある。この過程で、国際金融市場では、とくに為替市場において、そうした経済勢力の相対関係の変化と整合的な形で、結果的に円が増価したとみられる。
国内に眼を転じると、産業界は上記のような世界経済の主役交代に伴う量的、質的な環境変化への適応が求められている。すなわち、新興国の牽引力が、わが国産業が従来並みのスケールメリットを享受し続けるのに十分なものかどうかが不確実である一方、ボリューム・ゾーン(売れ筋商品)の機能性や価格帯が従来の先進国市場向けに比べて、簡素かつ安価な方向に変化している。今後のわが国経済について、企業や家計が経済的な福祉の向上を実感できるような持続的な成長を模索する上では、内外需バランスの是正といった議論よりも、製造業と非製造業といった切り口からの課題を考察する方が有意義。過去20年間の足取りを踏まえると、端的には、非製造業部門の労働生産性向上が優先課題。製造業においては、先端分野を含む多様な需要に応える創意工夫を伴った経営戦略が引き続き求められる。同時に、非製造業については、潜在的な需要を顕在化させ得るような施策と企業努力が期待される。それは、供給側の生産性向上を側面サポートする規制緩和等の政策と、その下での民間活力の発揮である。その際、需要する側としても、非製造業(卸・小売、サービス業など)が生み出す付加価値につき価格面を含めて適正に評価する意識改革が、産業構造の円滑な適応を促進する上でも必要かも知れない。
こうした状況を踏まえつつ、京都地区経済の活性化を考察すると、製造業がその技術力の優位性を活かして競争力を磨き続けると同時に、歴史や文化に裏打ちされた広義のサービス産業が、いわばソフト・パワーを研ぎ澄ますことが期待される。それは地域固有の強み(=京都力)を伸ばしていく運動法則(宝探し→宝磨き→宝伝えのサイクル)にも適っていると思われる。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|